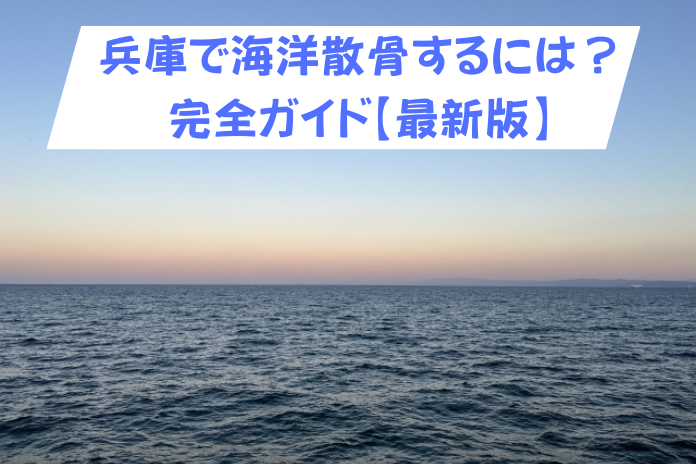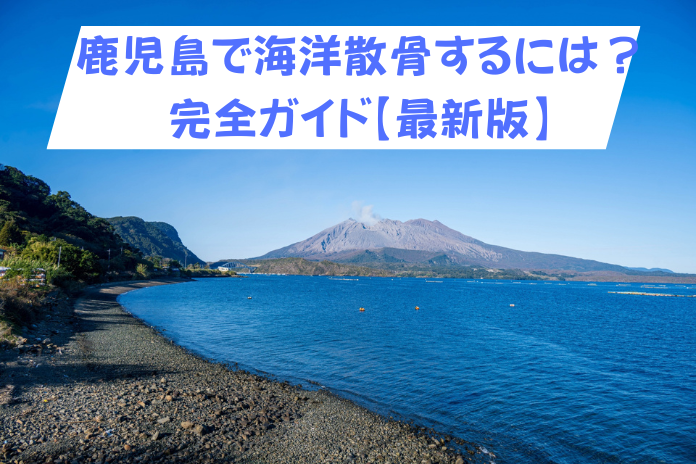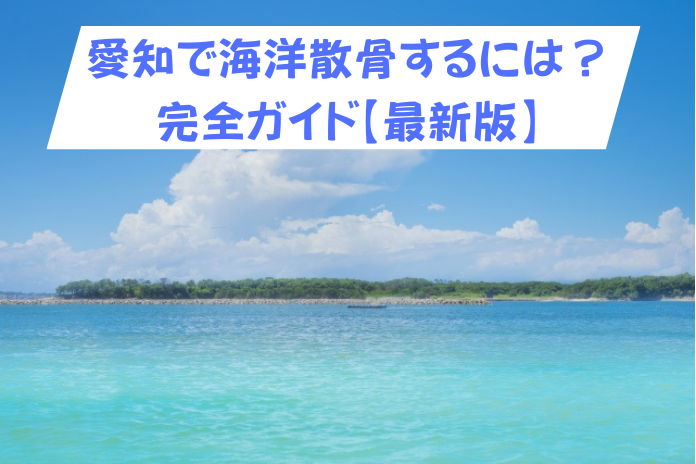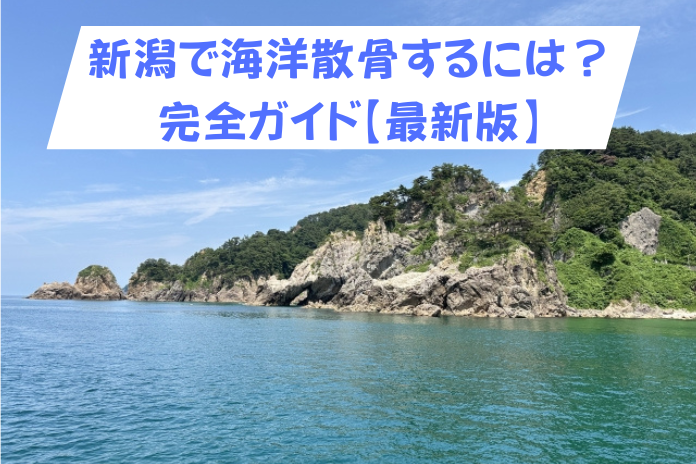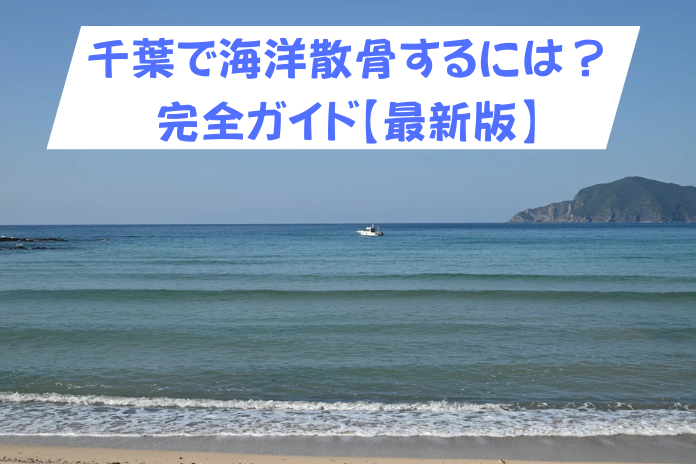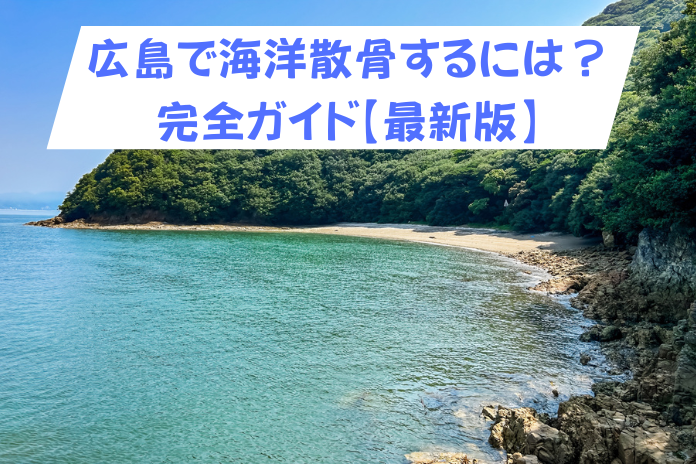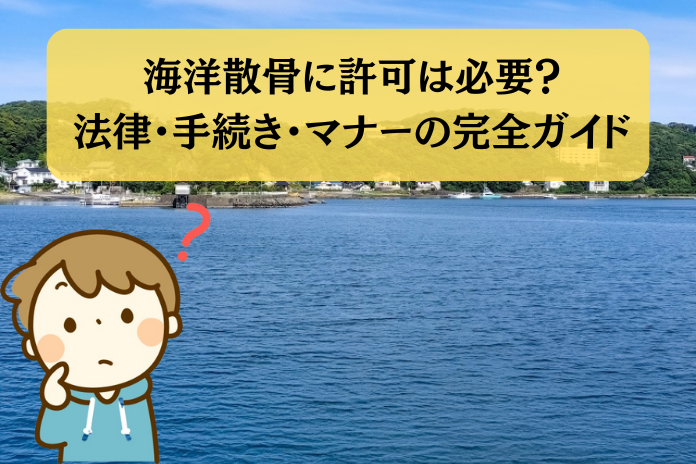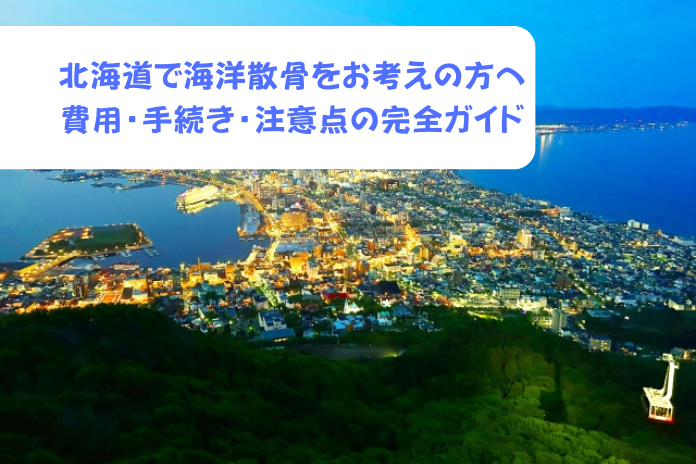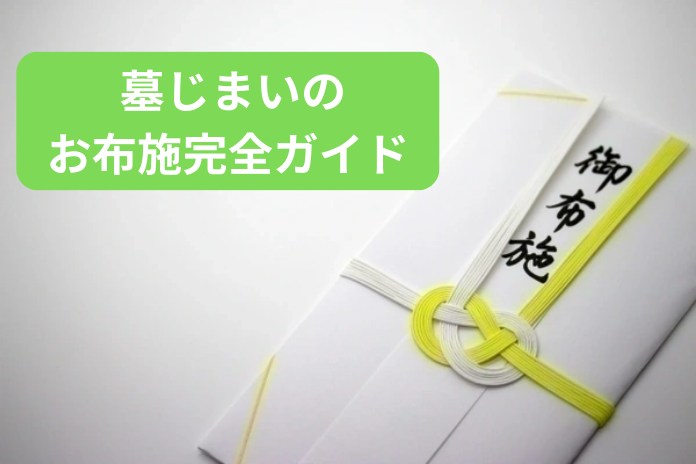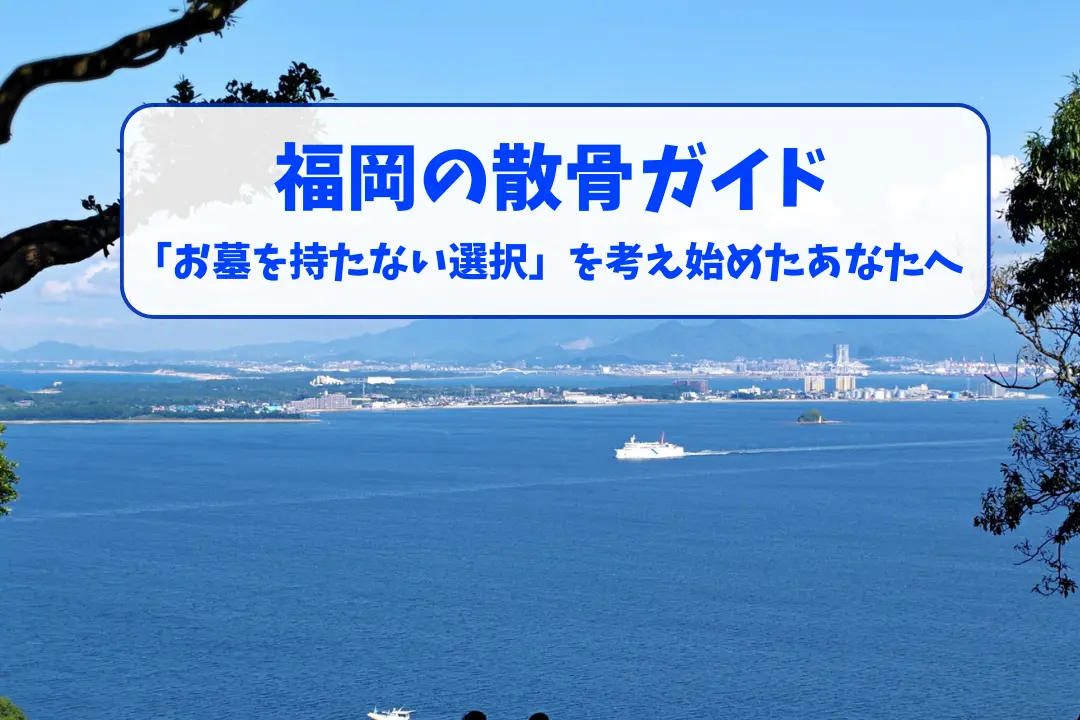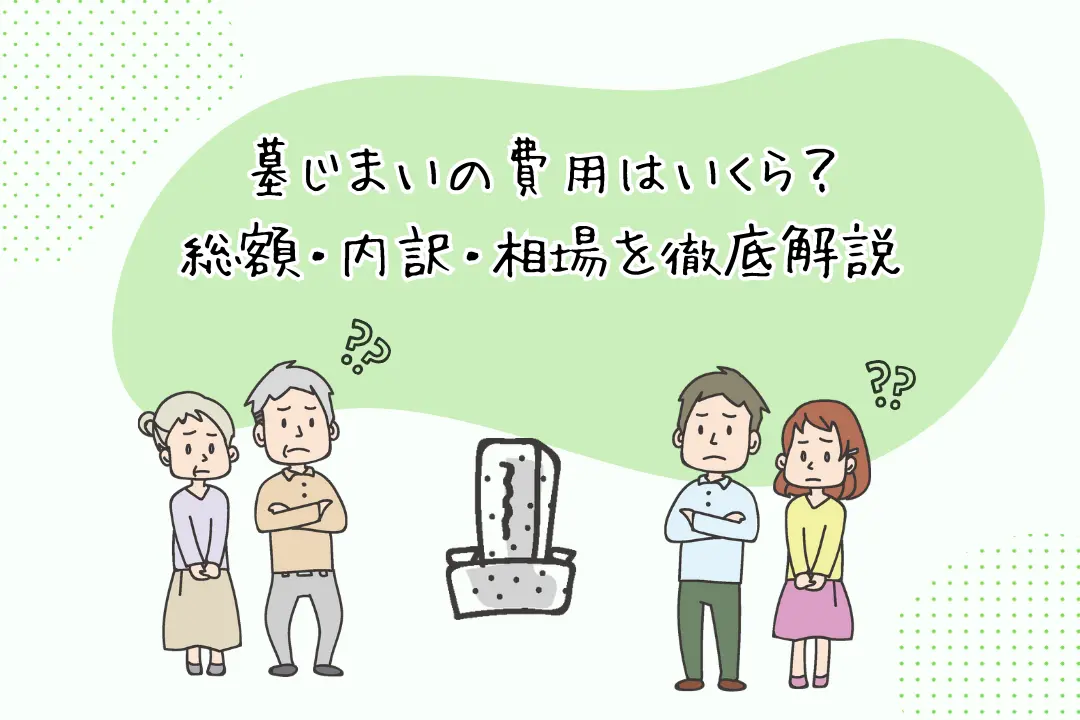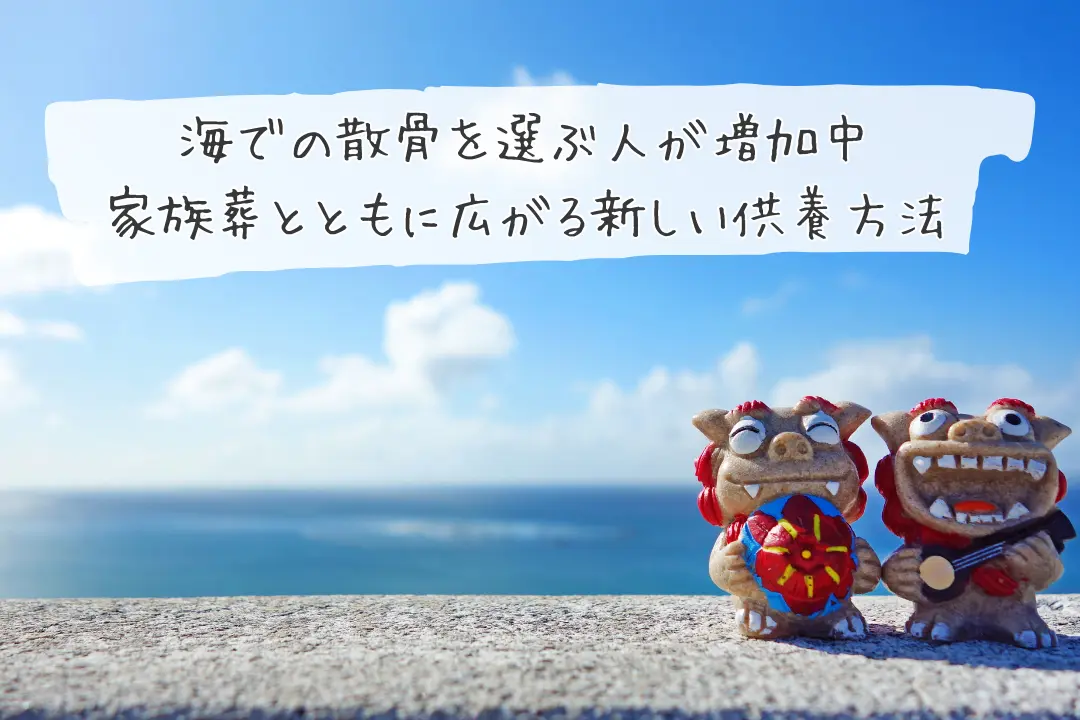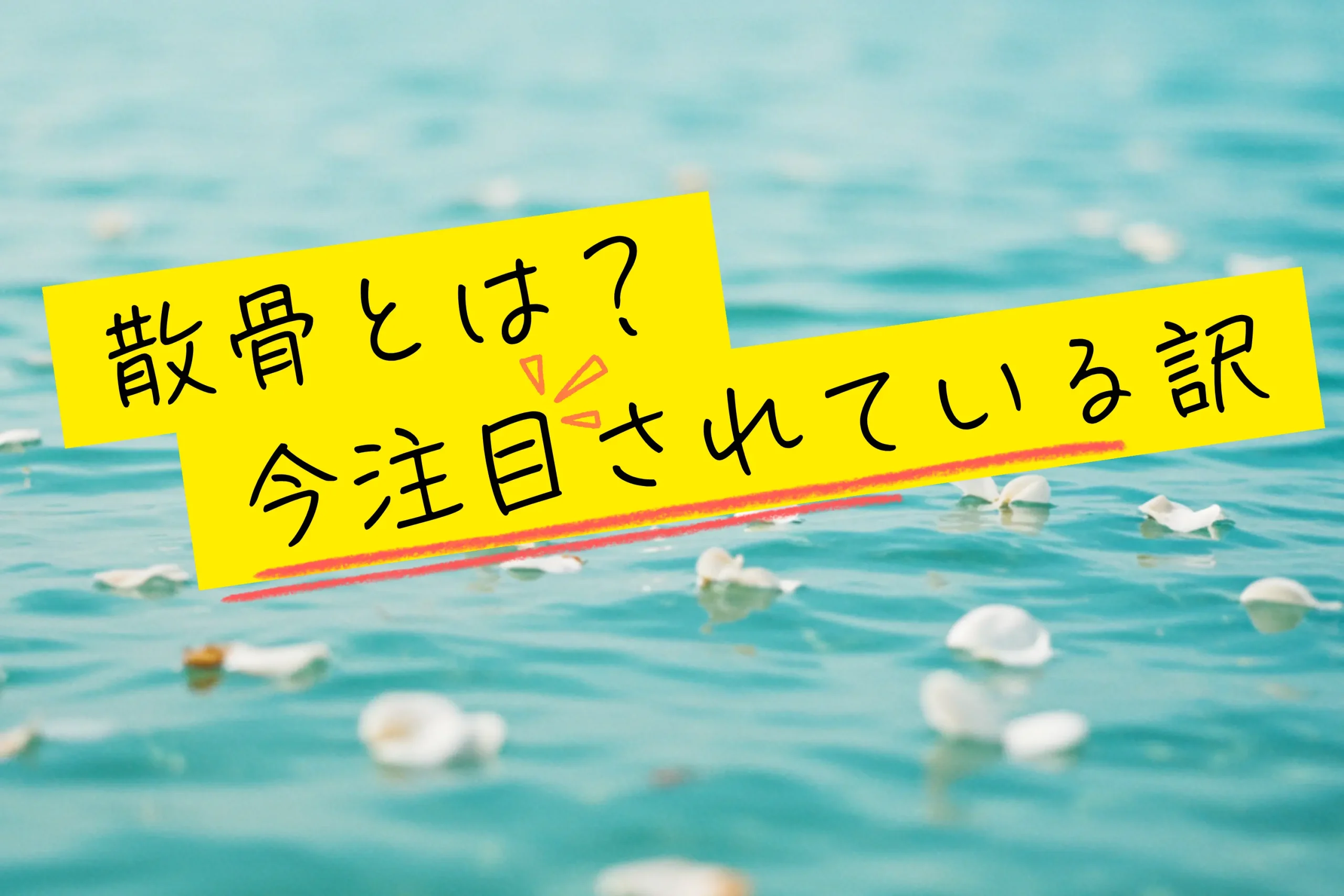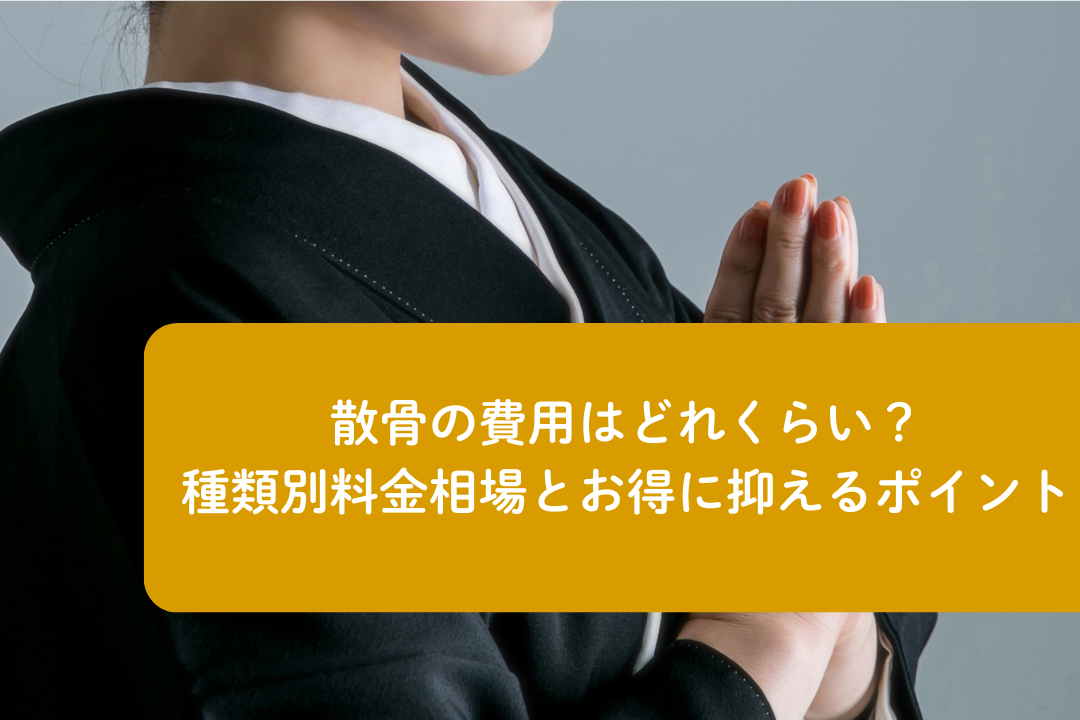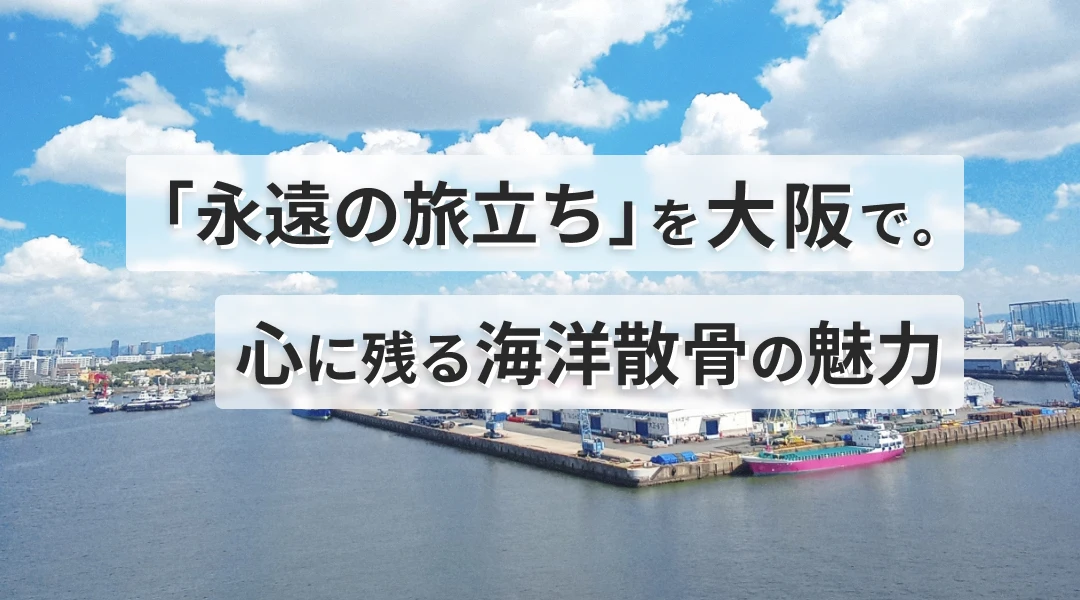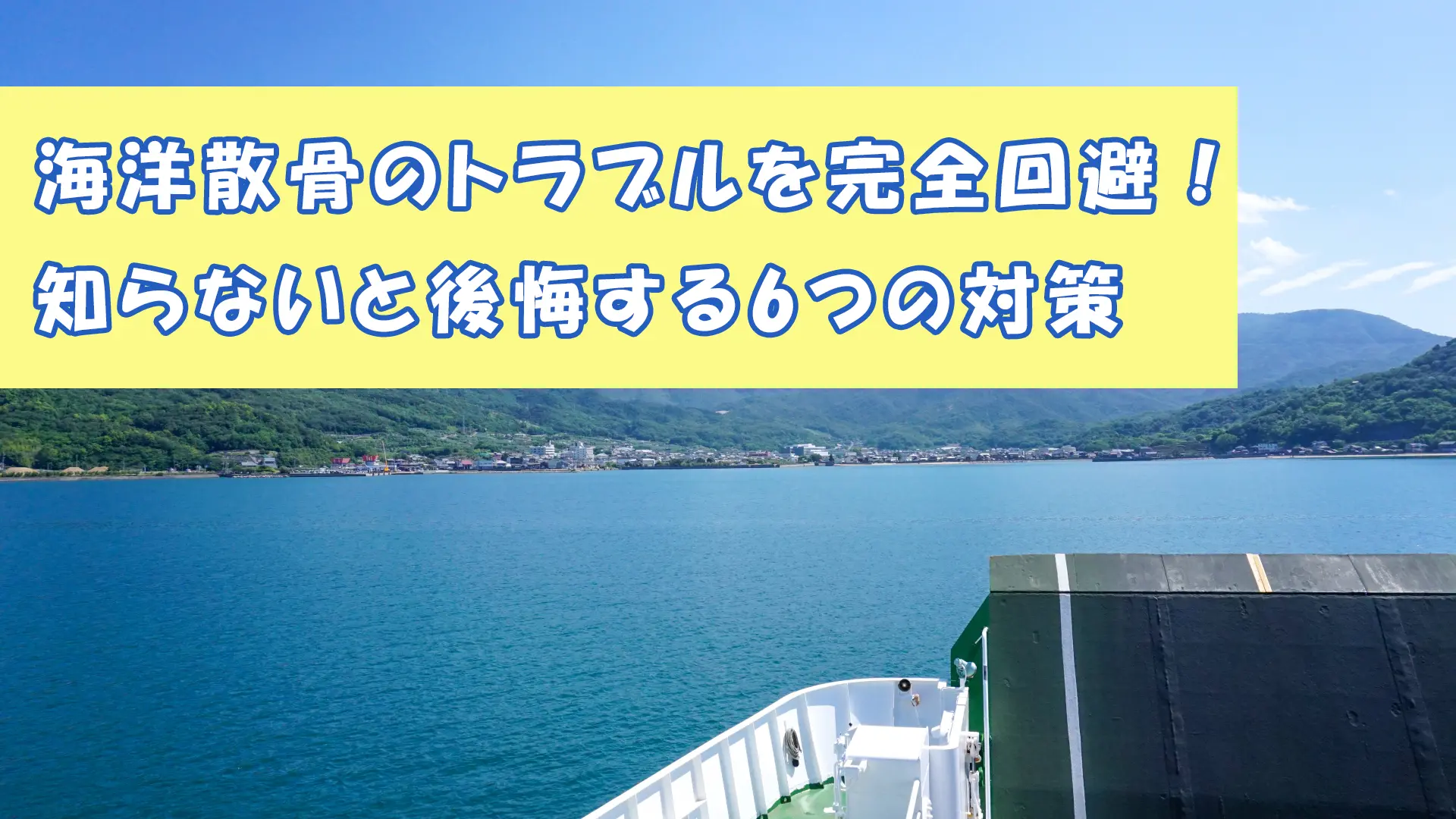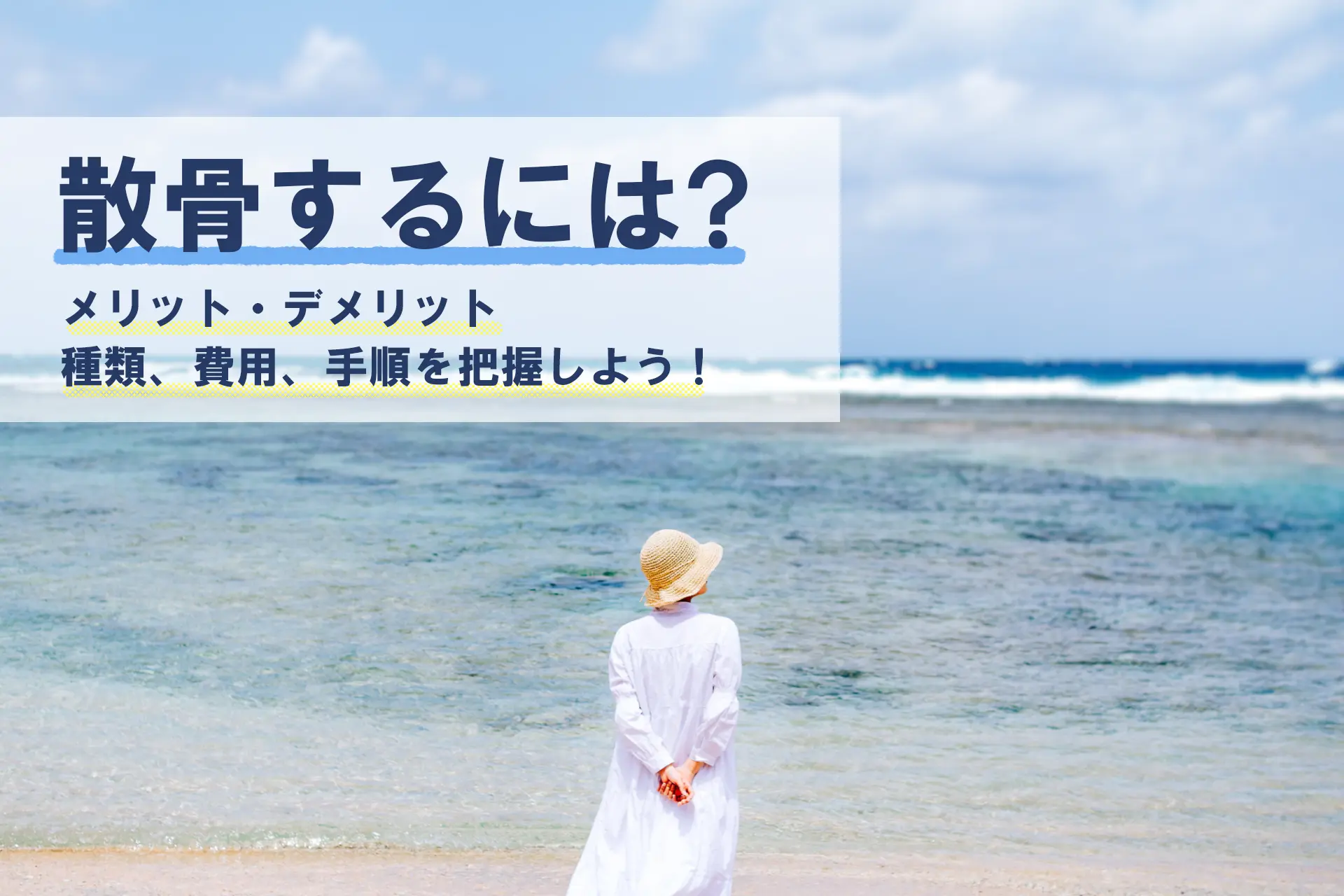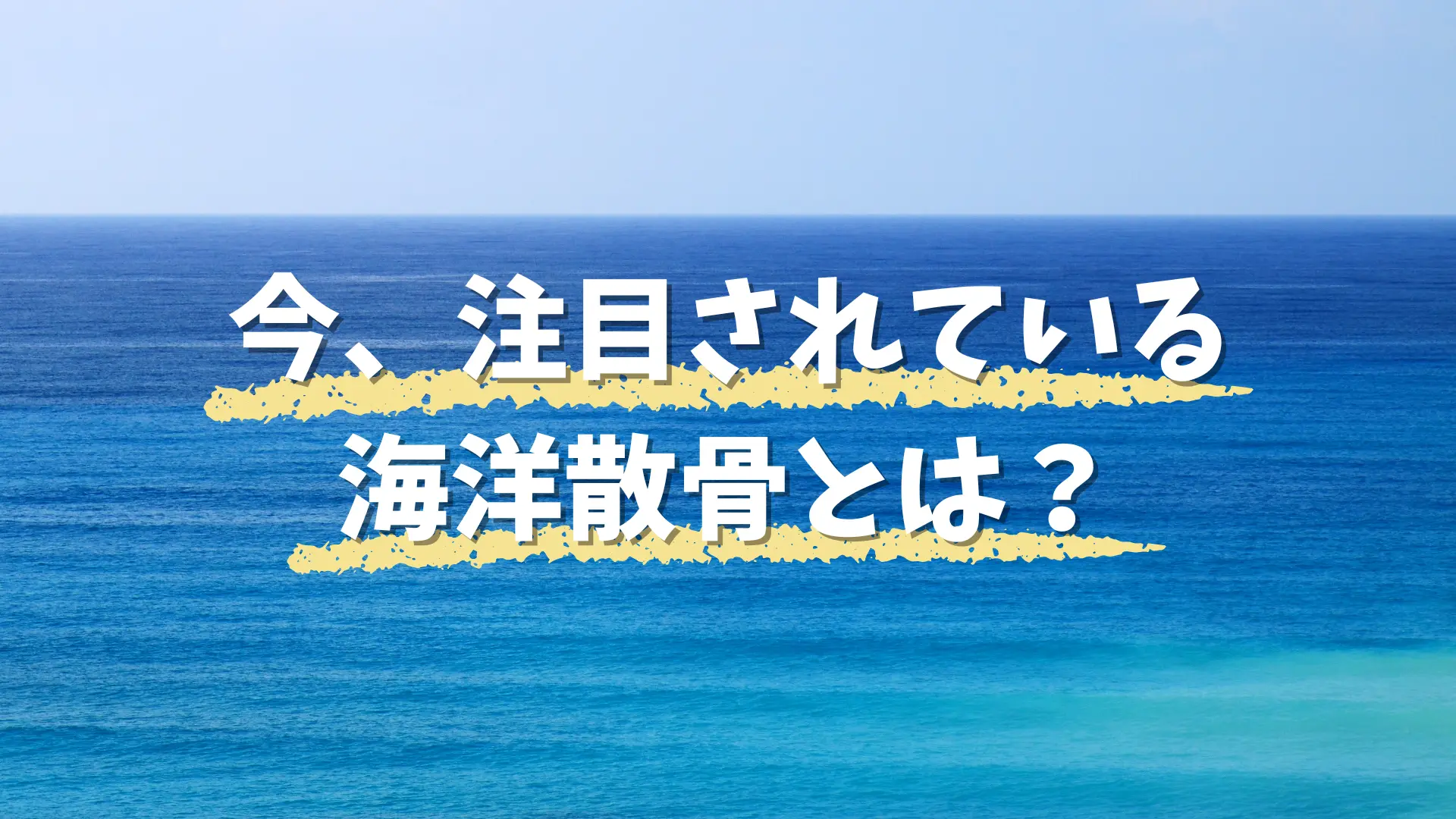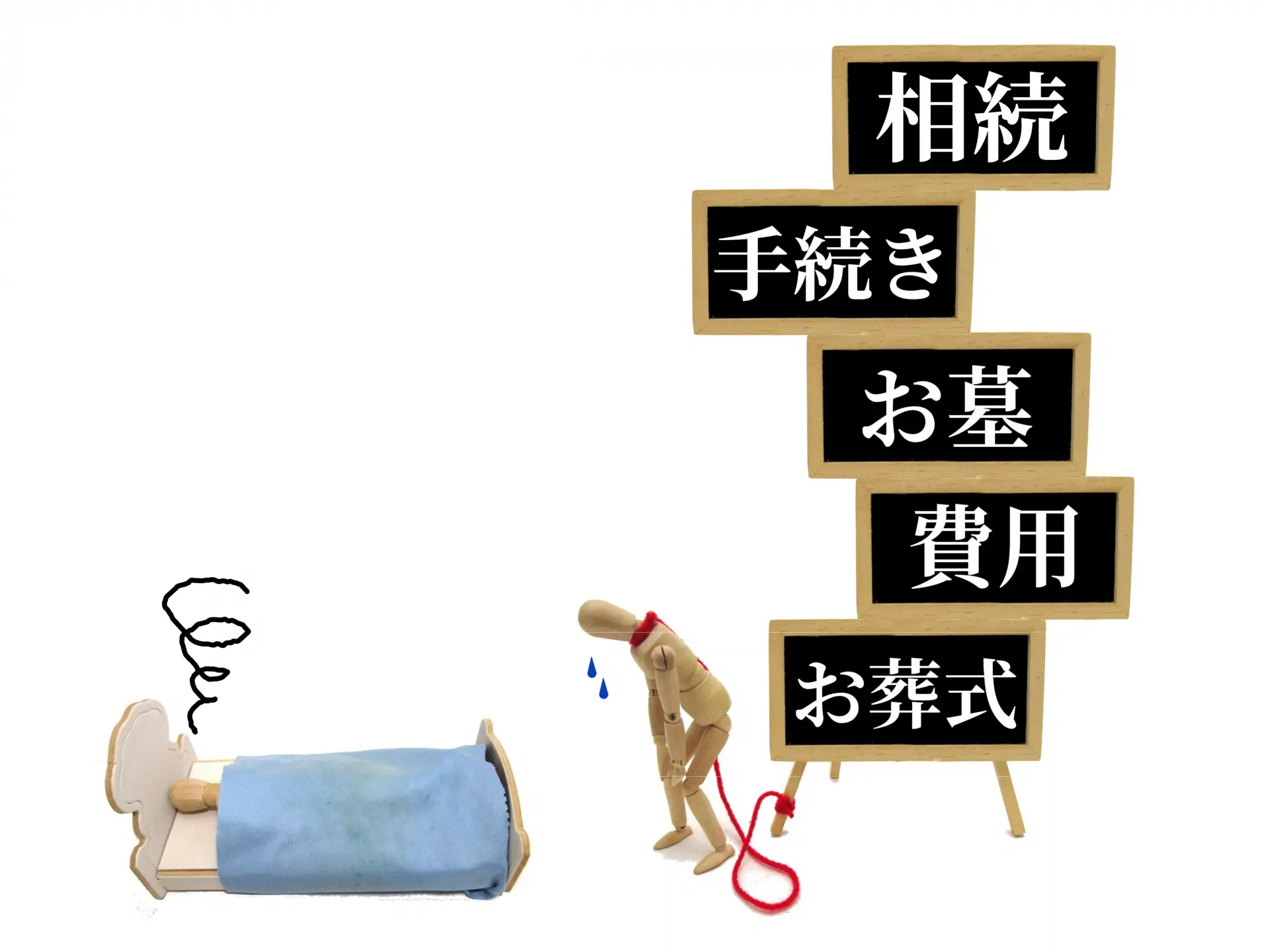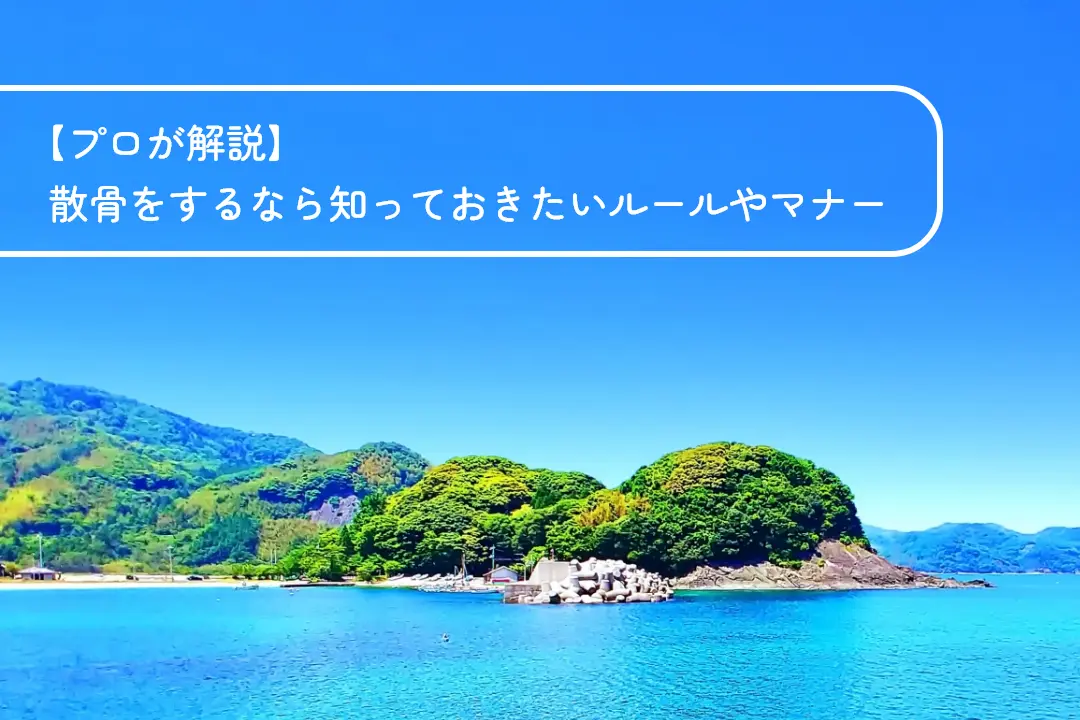気がつけば、誰も訪れなくなったお墓。
そこに眠る人の想いも、祈りも、少しずつ風化していくようで、どこか切ない。
最近、そんなお墓が全国で増えているといわれています。
「無縁墓地(むえんぼち)」誰にも供養されることなく、長い時間を過ごすお墓のことです。
少子化や家族のかたちの変化によって、これまで当たり前とされていた“お墓を受け継ぐ”という仕組みが、少しずつ難しくなってきました。
この記事では、無縁墓地とは何か、そして自分や家族がそうならないためにできることを整理していきます。
もしかしたら、「うちの話かもしれない」と思い当たることがあるかもしれません。
これからの供養のあり方を考える、ひとつのきっかけになれば嬉しいです。
そもそも“無縁墓地”とは?
無縁墓の定義と「無縁」とされる基準
「無縁墓」とは、継承者や管理者がいなくなり、供養や管理がされなくなったお墓のことを指します。正式には、一定期間以上、墓地の管理費が支払われなかったり、連絡が取れない状態が続いた場合に、墓地の管理者(市町村や霊園など)から「無縁墓」と判断されるケースが多いです。
民法や墓地埋葬法では明確な定義はないものの、「縁故者(えんこしゃ)が不明、または供養されない状態が長期にわたって続くこと」が判断基準とされています。
無縁墓地になると、具体的にどうなるのか
無縁墓と判断されたお墓は、墓地の管理者によって公告(一定期間、関係者に通知)された後、撤去や整理される可能性があります。この公告期間はおおよそ1年間程度とされ、連絡がなければ、そのお墓は「無縁」とみなされる流れとなります。
撤去された遺骨は、多くの場合「合葬墓(ごうそうぼ)」や「合同供養塔」といった場所にまとめて納骨されます。
形式的には供養されるとはいえ、個別のお墓という形はなくなり、名前も刻まれないまま埋葬されることも少なくありません。
誰かが訪れようとしても、故人を特定できる場所がないため、“手を合わせる場所がない”という状況になりがちです。
行政による撤去や合葬の可能性とは
特に公営墓地の場合、無縁と判断されたお墓は行政判断によって整理や撤去されるケースもあります。これは、墓地の管理上必要な措置とされ、放置された墓地が他の利用者に悪影響を及ぼさないようにするためのものです。
市町村によっては、定期的に無縁墓の調査や公告を行っており、「誰も気づかないままお墓がなくなっていた」という事例も実際にあります。
こうした措置は法律に基づいて粛々と行われる一方で、遺族や縁者にとっては、後から気づいたときのショックや後悔につながりやすい側面もあります。
なぜ今、無縁墓地が社会問題になっているのか?
墓守がいない家庭の増加(少子化・都市化の影響)
「お墓を継ぐ人がいない」「遠方で通えない」そんな声が今、全国各地で現実になりつつあります。
背景にあるのは、少子化と都市部への人口集中です。
地方にある実家のお墓を、都会に住む子世代が守り続けるのは、時間的にも経済的にも簡単ではありません。
かつては当たり前だった「長男が家を継ぎ、お墓も守る」という構図も、現代では成り立たなくなりつつあります。
結果として、“管理されないお墓”が増え、それが無縁墓地として社会問題化しているのです。
「子どもに迷惑をかけたくない」という意識の変化
以前は、「立派なお墓を建てることが供養になる」と考える人が多くいました。しかし近年では、「子どもに負担をかけたくない」「墓守を押しつけたくない」という意識が広がりつつあります。
その背景には、価値観の変化だけでなく、現実的な経済事情や家族構成の変化もあります。
子どもがそもそもいない、独身、遠方にいる。
そんな状況下で、「お墓はあっても、管理が続かないのでは」と不安に感じる人は年々増えています。
“自分の代で終わるかもしれない”という前提に立った供養の選択が、現実味を帯びてきているのです。
もはや他人事ではない、身近にある無縁のリスク
「無縁墓地」と聞くと、遠い誰かの話のように感じるかもしれません。ですが、実際には、ごく普通の家庭でも数十年後には無縁化するリスクがあるというのが今の時代の現実です。
・子どもがいない
・子どもが供養に興味がない
・距離や事情で、お墓参りができなくなる
・お墓がどこにあるかすら知らない世代が増える
こうした小さな“継承の断絶”が、いつの間にか無縁を招く要因になります。
「うちは大丈夫」と思っていても、時間とともに状況は変わるもの。
今から少しずつ備えておくことが、家族の心を守ることにもつながるのです。
無縁墓地にならないためにできる3つの対策
墓じまいや改葬をして負担を減らす
お墓の継承が難しいと感じたとき、まず考えたいのが「墓じまい」です。墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移すこと(改葬)を指します。
近年では、親世代のお墓を墓じまいして、
・永代供養墓や合葬墓に納める
・自分の近くの納骨堂に移す
など、無理のない場所や形で供養し直す人が増えています。
「申し訳ない」「寂しい」という気持ちを抱える人もいますが、
管理できずに無縁になってしまうより、“今できる供養”を選ぶことこそが、供養の本質なのかもしれません。
永代供養や納骨堂など継承不要の選択肢
墓じまいをした後や、新たにお墓を考える際に注目されているのが、永代供養や納骨堂です。
永代供養墓:寺院や霊園が遺骨を長期にわたり管理や供養してくれる仕組み。継承者不要。
納骨堂:屋内型でアクセスが良く、手元供養や一部納骨との併用も可能。
これらの選択肢は、将来にわたって無縁にならない仕組みが整っているのが最大のメリットです。
「誰かに守ってもらうお墓」から、
「仕組みで守られる供養」へ。
今は、そんなスタイルが当たり前になりつつあります。
「自然に還る」散骨という新しい供養のかたち
最近、選ぶ人が増えているのが「散骨」です。中でも海や山に遺骨を還す“自然葬”としての散骨は、お墓を持たない供養として注目を集めています。
・継承者が不要
・管理費や墓石の維持費がかからない
・「自然の中で眠りたい」という本人の希望にも応えられる
家族の気持ちの整理や、「ちゃんと送れた」という納得感が得られるよう、
花や手紙を添える、セレモニーを行うなど、“心を込めた散骨”を選ぶ人も増えています。
「墓を持たない」=「供養をしない」ではなく、
自分らしい、家族らしい供養を大切にするという考え方が広がってきています。
家族で考える、供養の“これから”
まだ元気なうちに話しておくこと
お墓や供養の話は、つい後回しにされがちです。「縁起でもない」「そのうち考えよう」と思っているうちに、タイミングを逃してしまうことも少なくありません。
でも実は、元気なときこそが、家族で本音を話しやすい唯一の時期です。
・自分はどう供養されたいか
・家族にはどんな形が負担が少ないか
・墓を建てるのか、建てないのか
そうしたことを、想像ではなく、言葉で確認するだけで、後悔や不安の多くは減らせます。
墓を持たない人生設計と心の納得
「お墓は当たり前」という価値観が、少しずつ変わってきています。今は、墓を持たないという選択も、人生設計の一部として自然な時代になりました。
もちろん、お墓を建てることも素晴らしい供養ですが、それ以外にも
・散骨
・納骨堂
・手元供養
・永代供養墓
など、管理するのではなく想いを残す供養が広がっています。
どのかたちが正しいかではなく、
自分たちにとって無理がなく、納得できるかどうか。
その視点で供養を選ぶ人が増えているのも、今の時代ならではの傾向です。
「ちゃんと送る」ことの意味を見つめ直す
形式ではなく、気持ちがこもっていること。立派なお墓があるかどうかよりも、故人のことを想い、大切に見送ること。
それが、本当の意味での供養なのかもしれません。
「無縁にならないように」と考えるのも大切なこと。
でもそれ以上に、誰かの記憶にちゃんと残り、誰かの心にちゃんと寄り添えることが、供養の本質だと気づかされる場面もあります。
家族で話す、考える、選ぶ。
その積み重ねが、きっと“ちゃんと送れた”という安心感につながっていきます。
納得できる選択をするために|銀河ステージのご案内
さまざまな供養スタイルを知る第一歩に
供養のかたちは一つではありません。大切なのは、自分や家族にとって“ちょうどいい”送り方を見つけること。
でも、いざ調べようと思っても、どこから始めていいか分からない
そんな方にこそおすすめしたいのが、銀河ステージという散骨専門業者です。
銀河ステージでは、無料で資料請求や相談が可能。
気になるプランを比較しながら、「いま決めなくても、ちゃんと選べる」安心感が得られるのも魅力です。
資料を取り寄せたり、問い合わせてみたりすることが、後悔しない選択につながります。
自分と家族に合った“供養のかたち”を見つけるために
このコラムを読みながら、
「うちの場合はどうだろう」「自分だったらどうしたいだろう」
そんなふうに、少しでも供養のことを考えるきっかけになったなら、それだけでもとても大きな一歩です。
誰かにとっての正解が、自分にとっての正解とは限らない。
だからこそ、自分たちらしいかたちを見つけるために、選択肢を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
あなたとご家族にとって、納得のいく供養のかたちが見つかりますように。