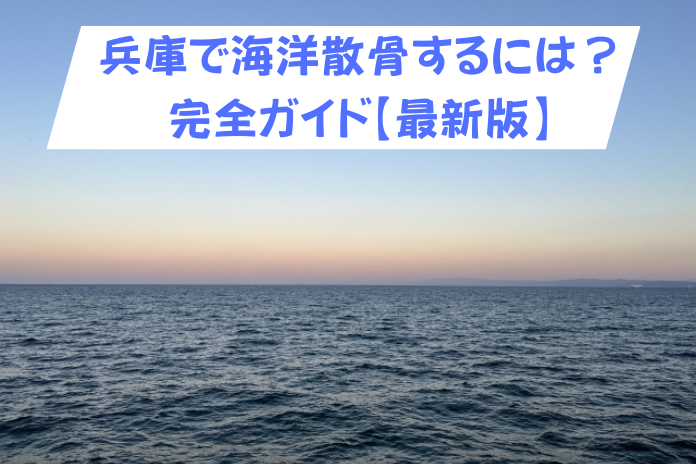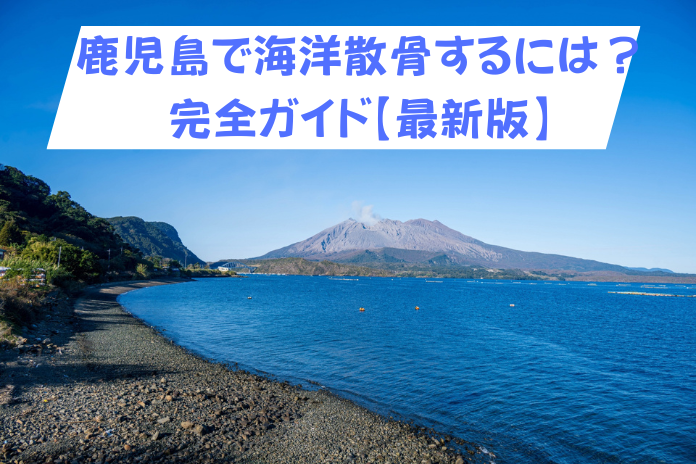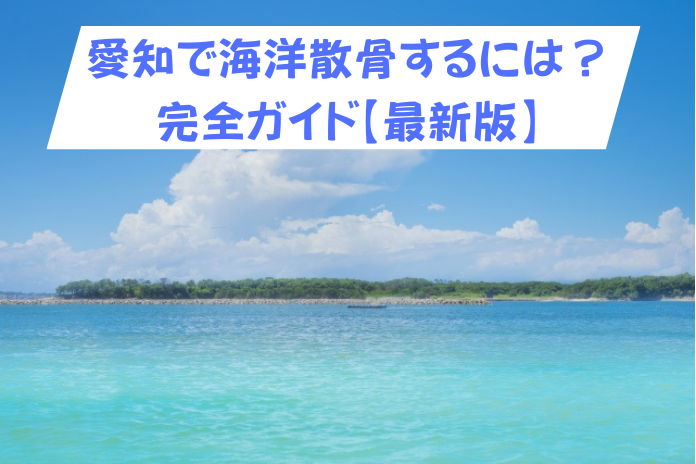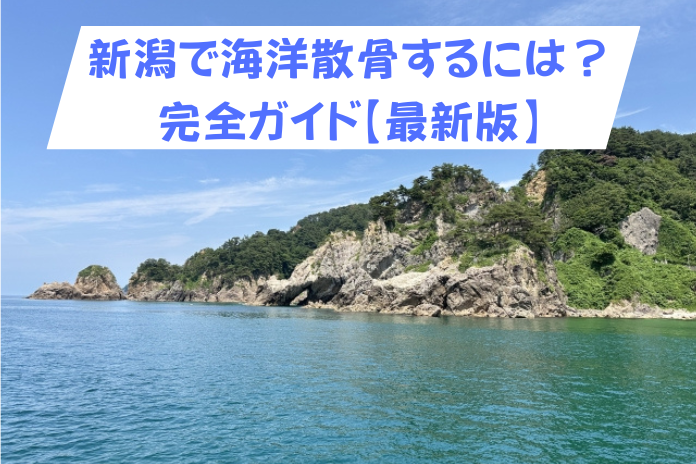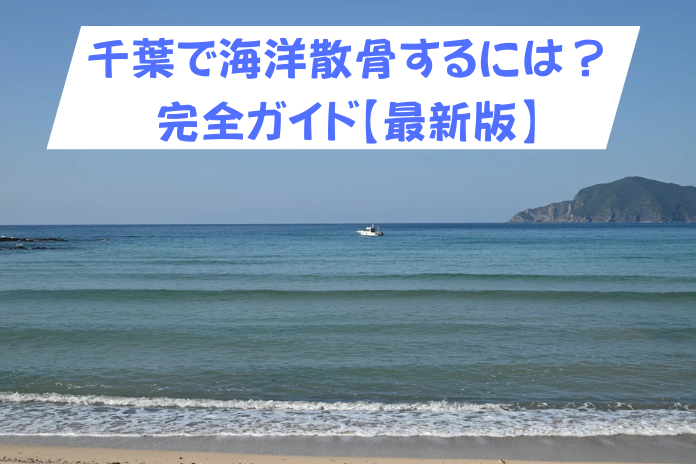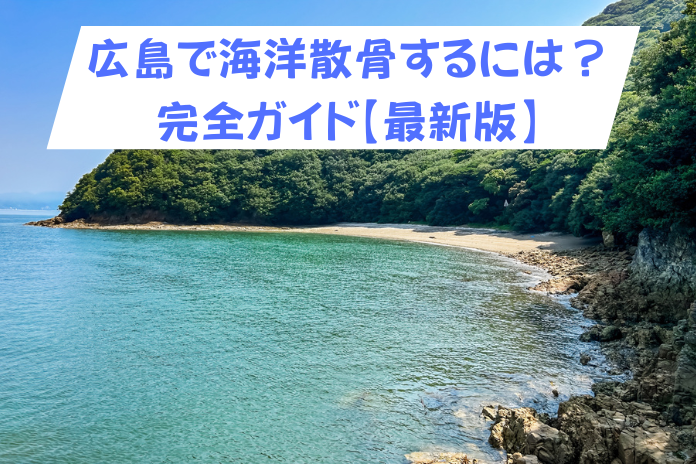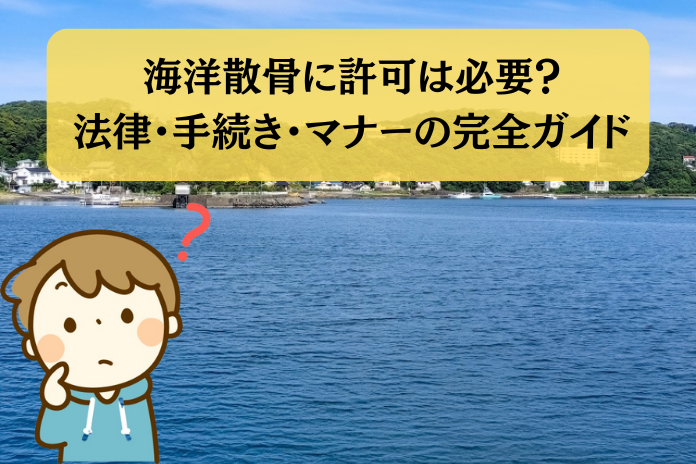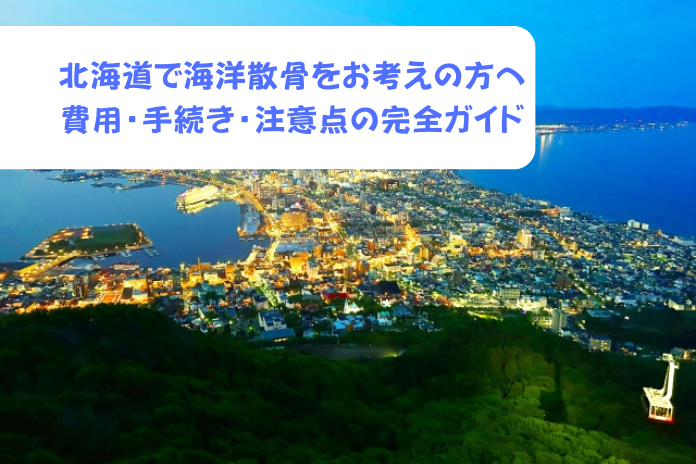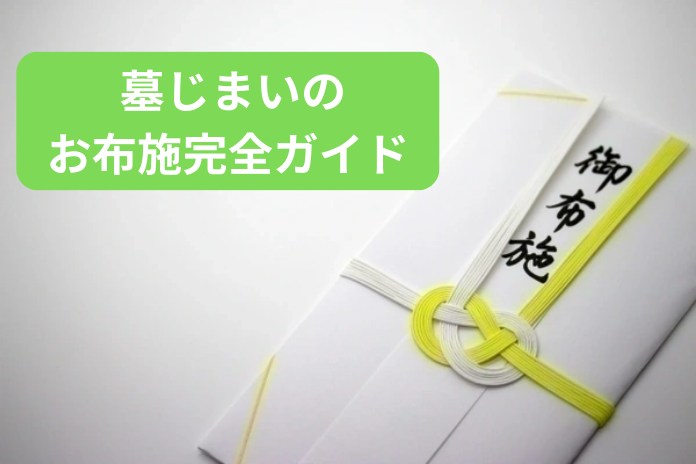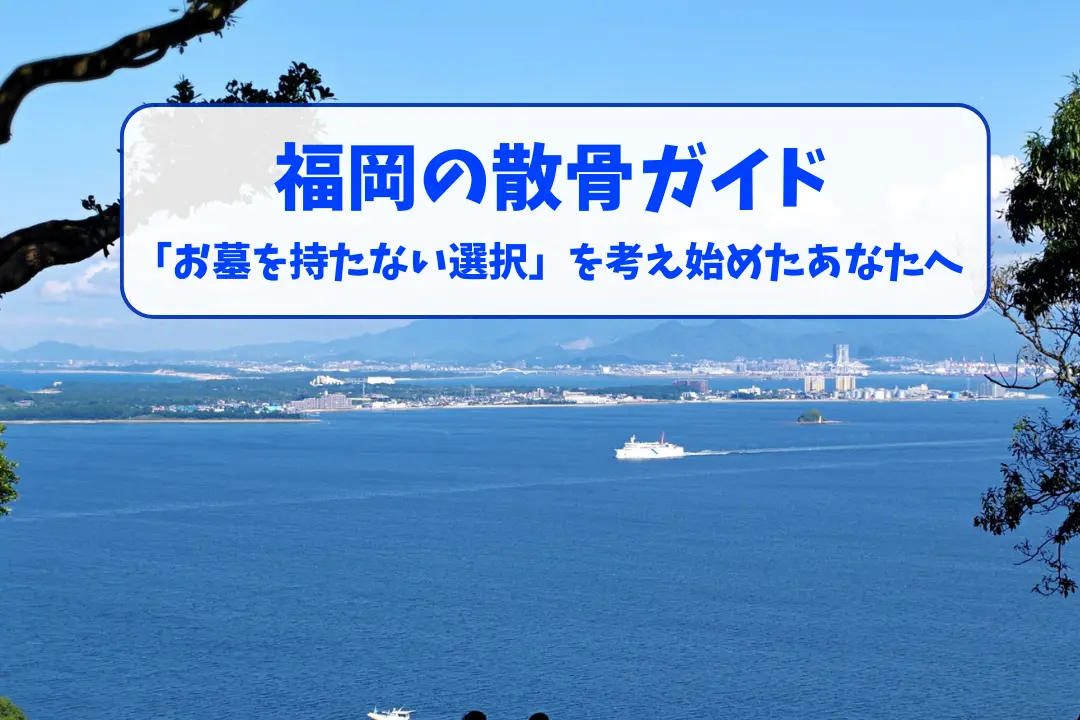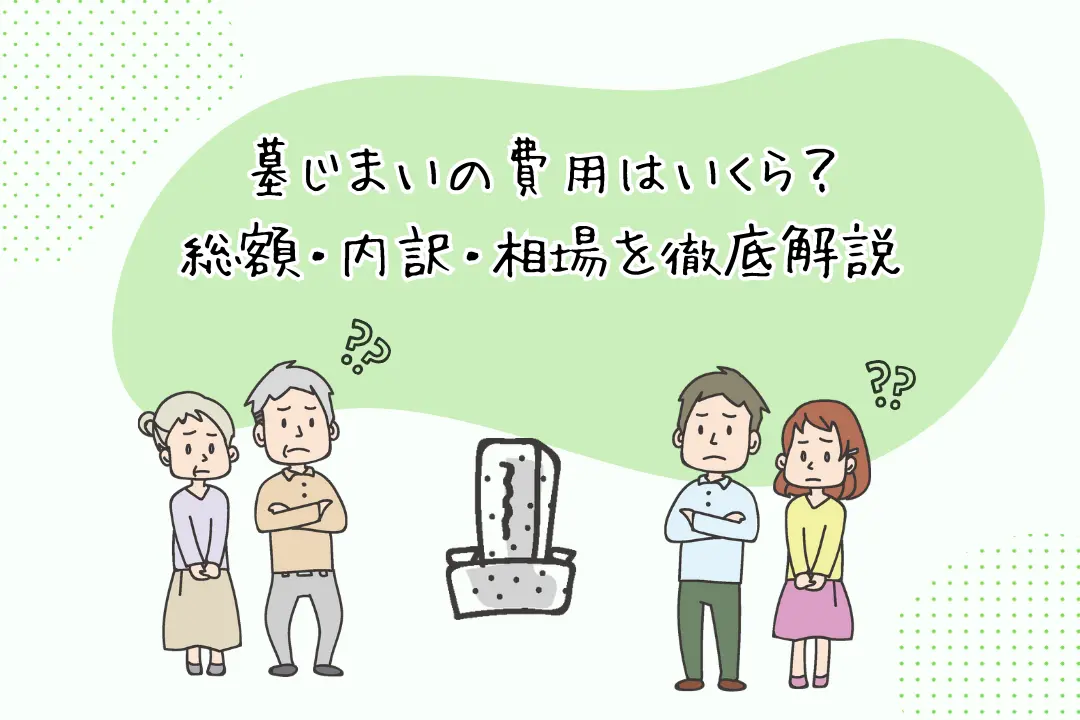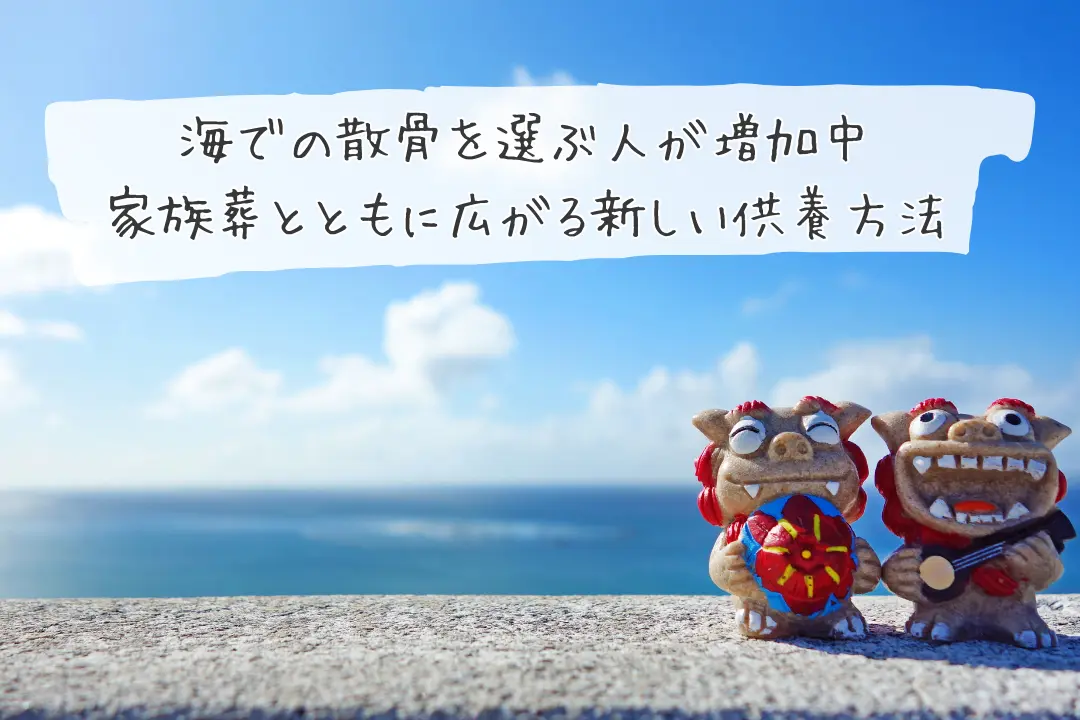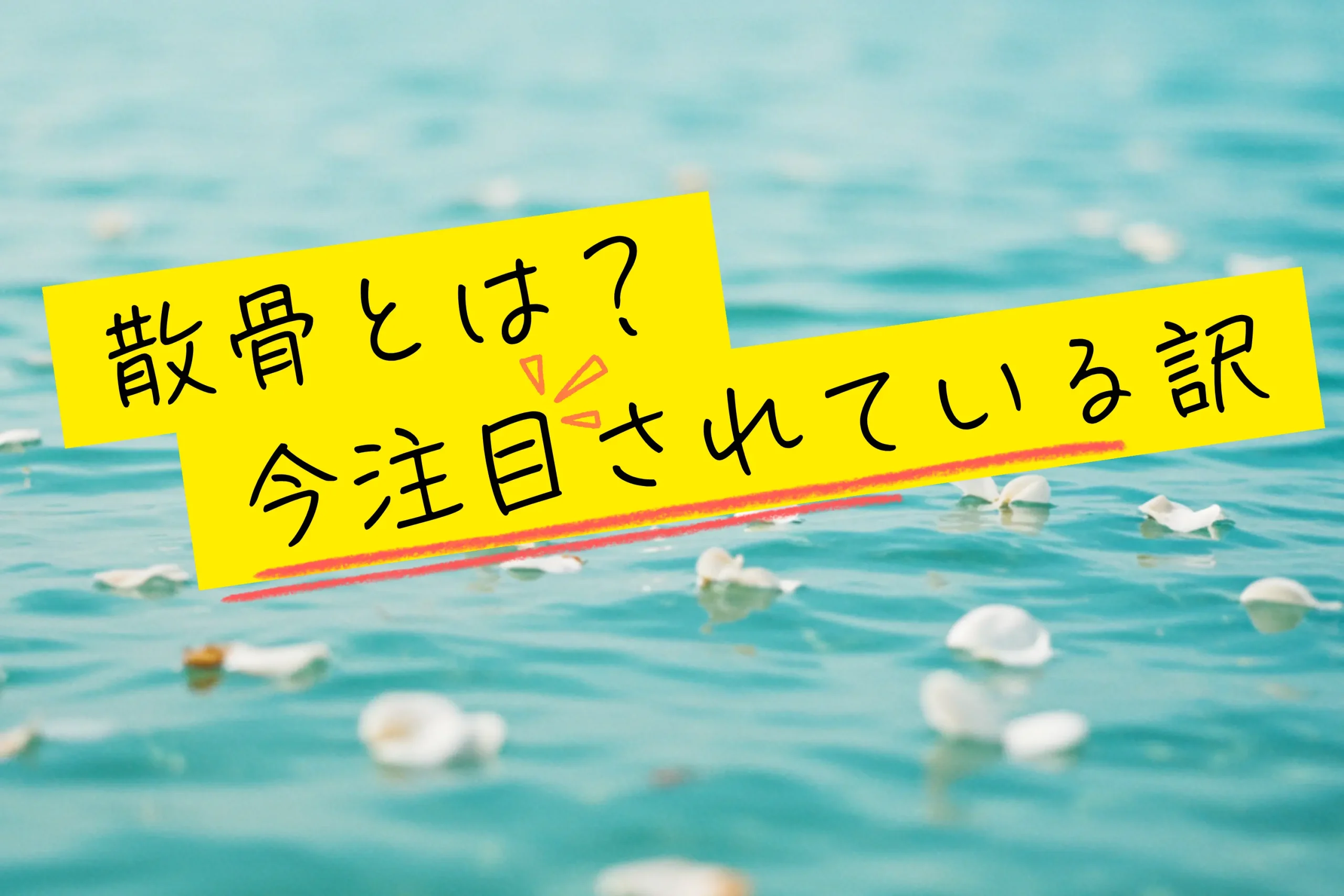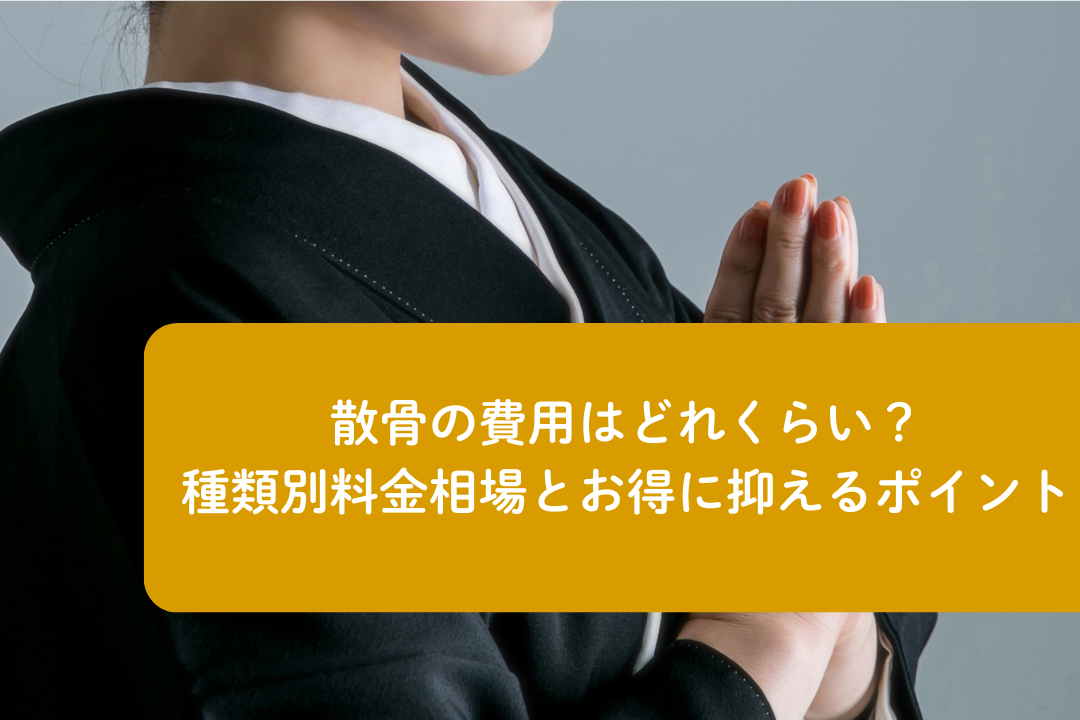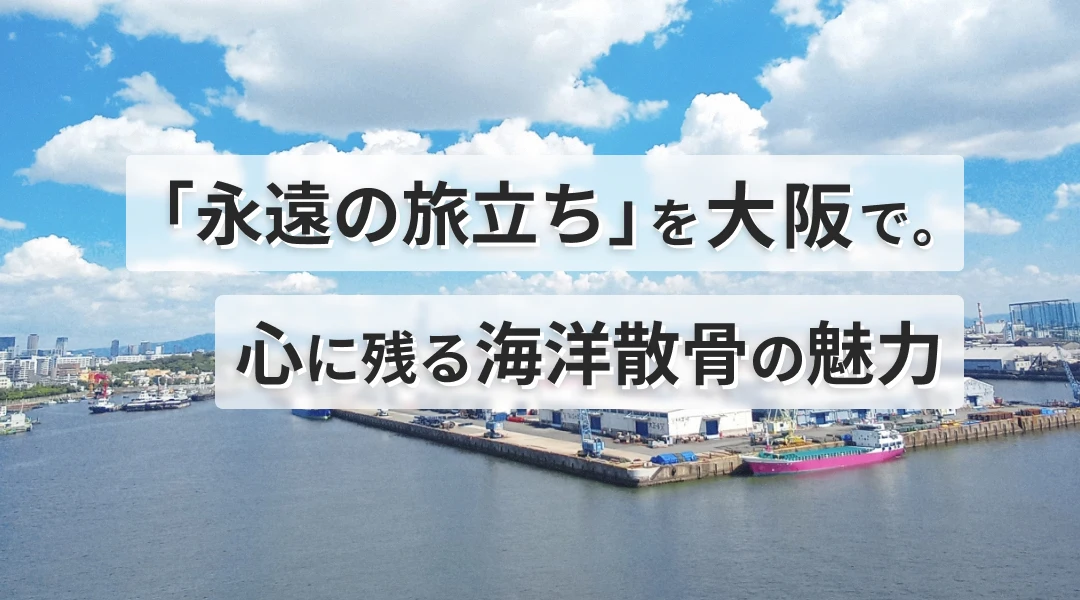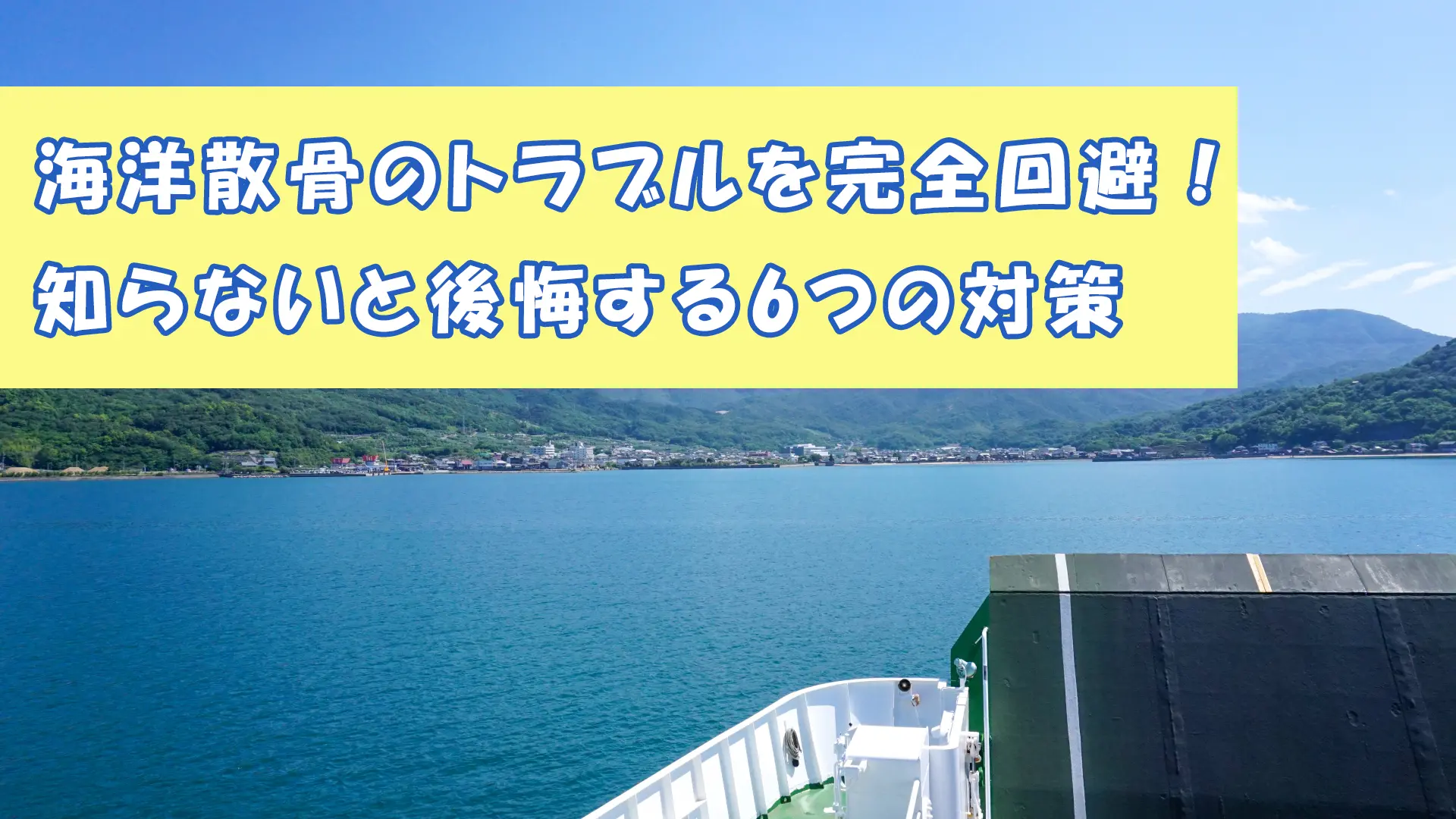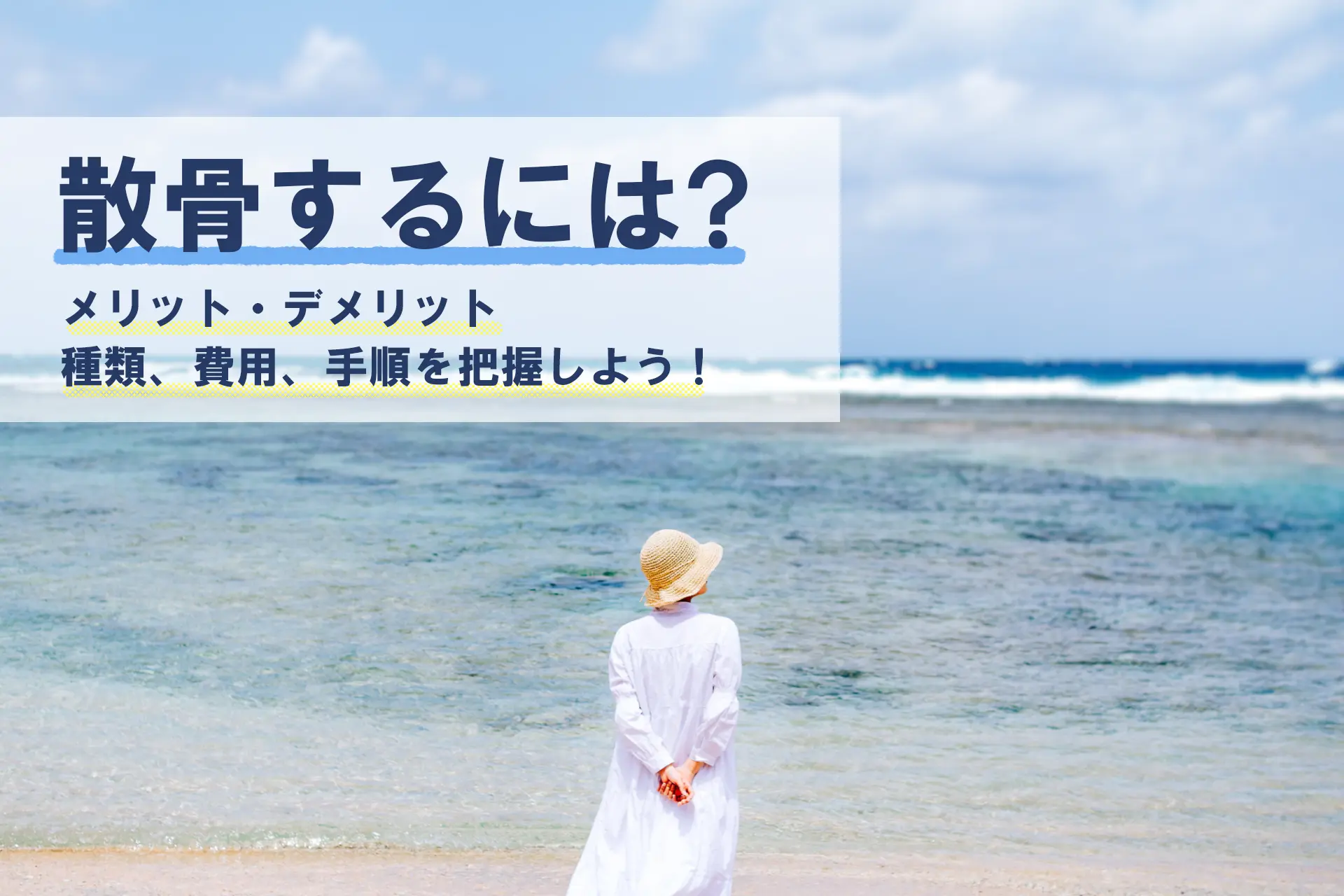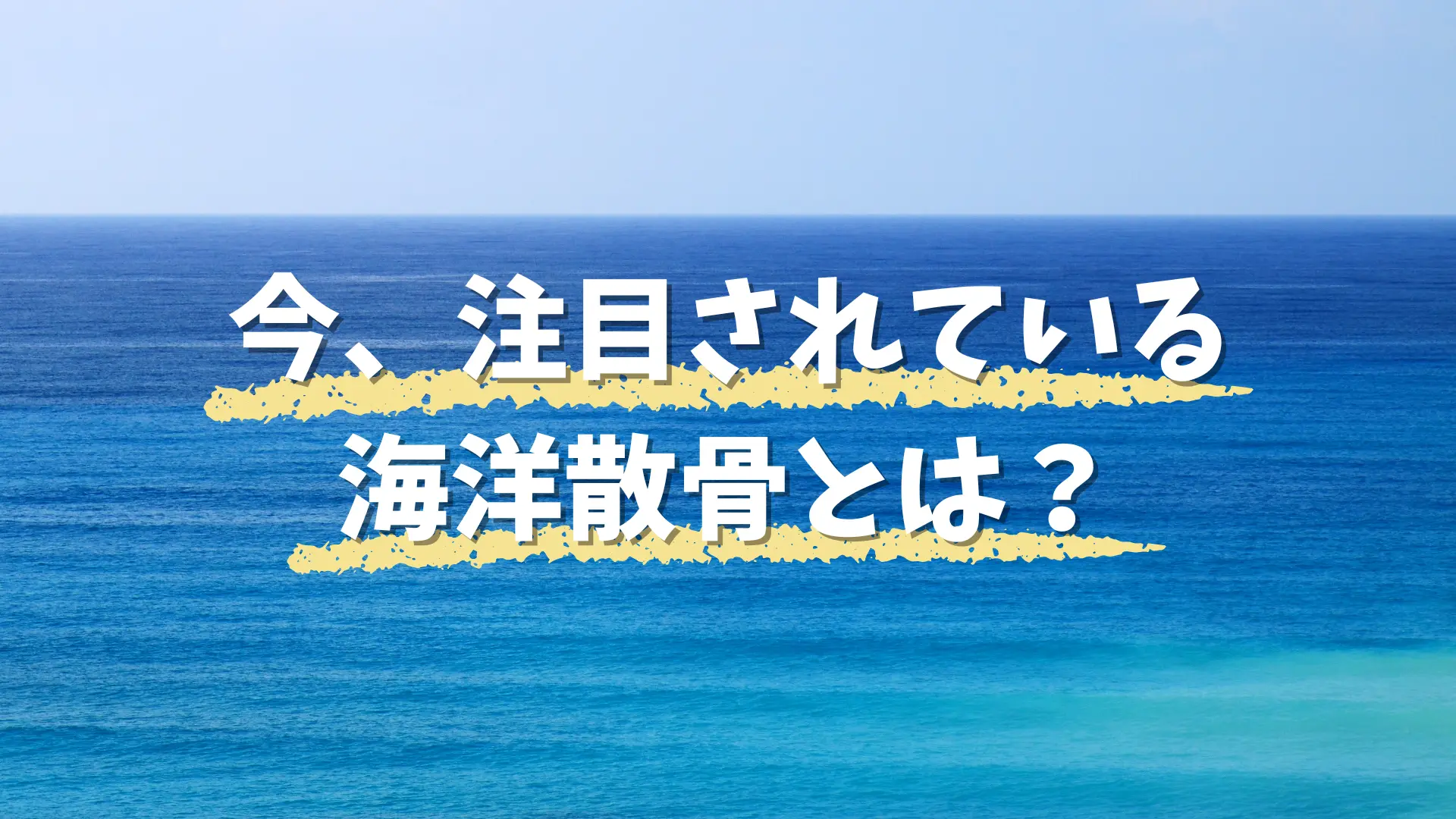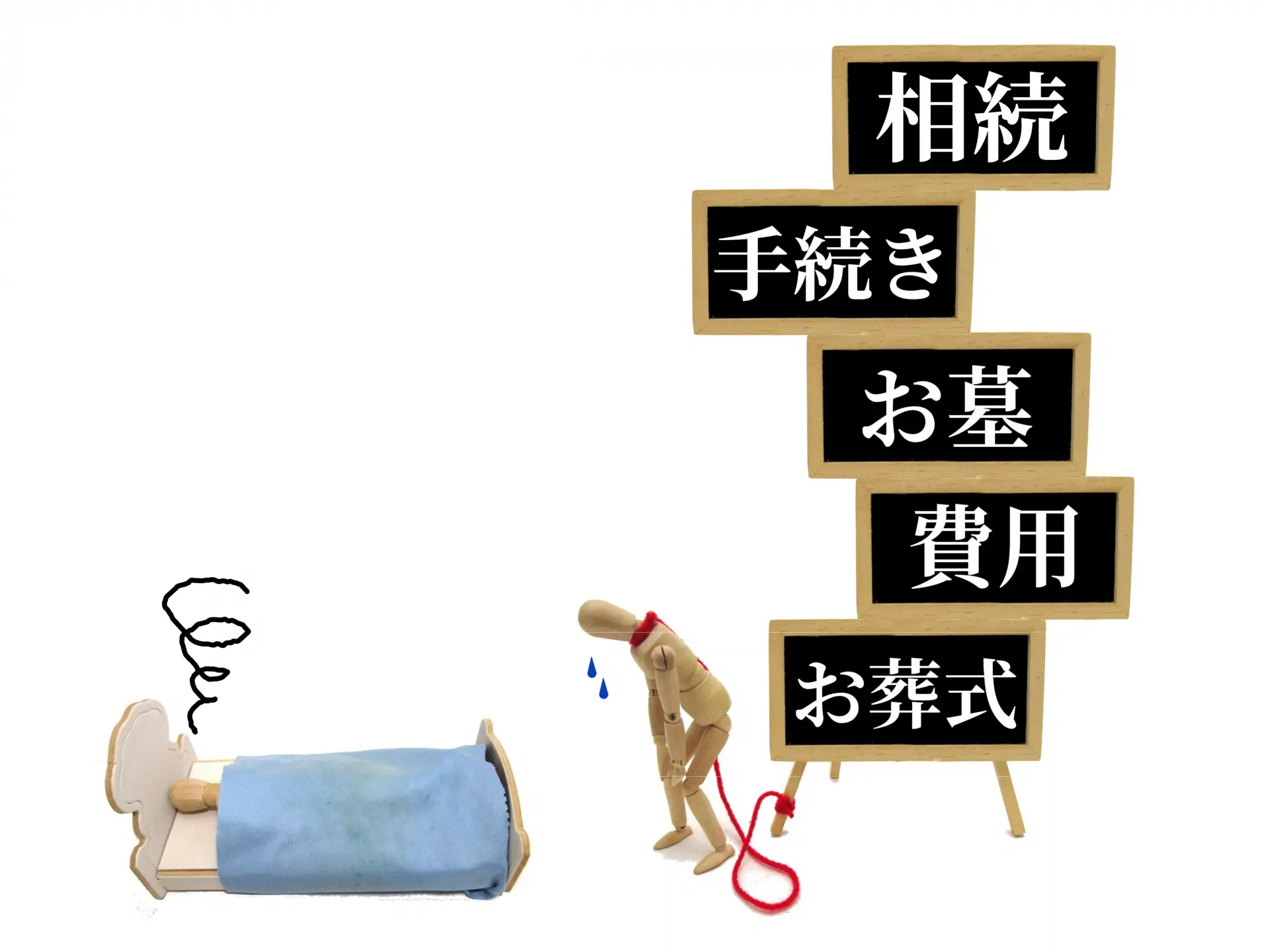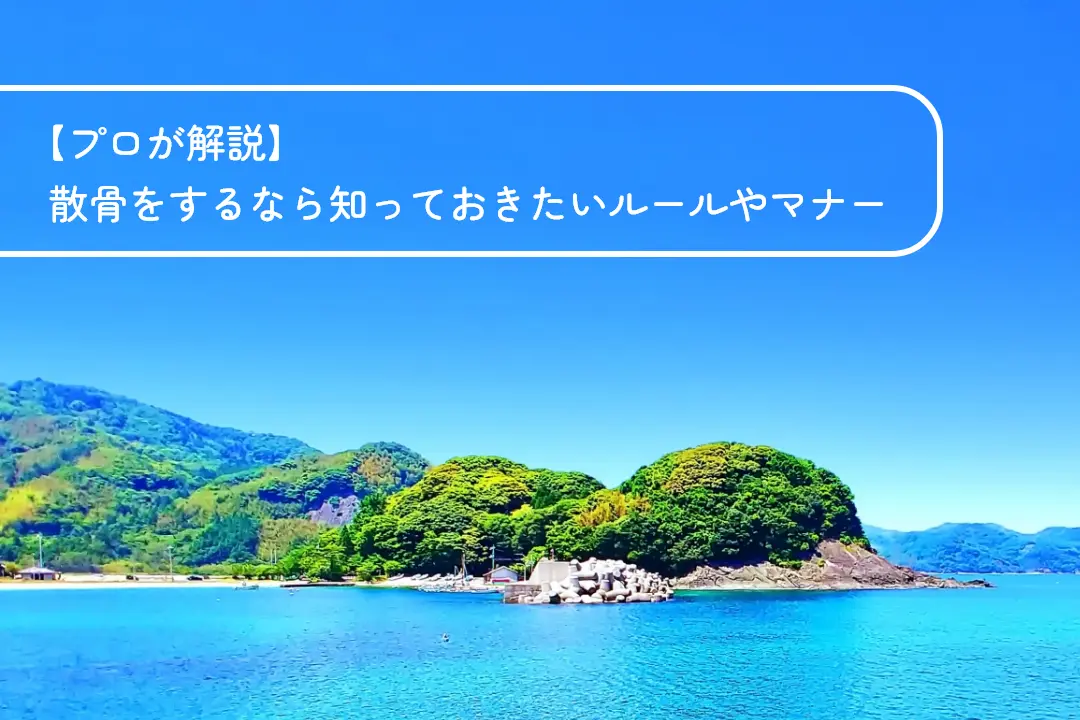「うちは代々このお墓を守ってきたから」
そんな言葉が当たり前だった時代も、今では変わりつつあります。
近年、日本では「お墓を持たない」選択や「墓じまい」が急増しています。
人口構造やライフスタイルの変化にともない、お墓のあり方が見直されるようになりました。
この記事では、日本のお墓事情の現状とその背景、新しく注目されている供養スタイルについて詳しく見ていきます。
日本のお墓事情2025年|なぜ今“変化”が起きているのか?
【変化1】かつては“守るもの”だったお墓
昔の日本では、お墓は“家族そのもの”を象徴する存在でした。
家制度が根強かった時代、ひとつの家族にひとつのお墓があり、そこに代々入るのが当たり前。
お盆やお彼岸には親戚が集まり、ご先祖さまへ手を合わせるそんな風景が、どこの地域でも見られたものです。
お墓には、「つながり」を感じさせる力がありました。
家族の歴史を実感できたり、大切な人を想い返すきっかけになったり。
それは、誰かに言われて守るというより、自然と大事にしたくなるものだったのかもしれません。
【変化2】核家族化と高齢化で「お墓の継承」が難しくなった
家族のかたちが変わったことで、お墓との向き合い方にも、大きな変化が起きています。
昔のように「親と同居して、先祖代々のお墓を守る」というスタイルは、今では少数派になりました。
核家族化が進み、親子が離れて暮らすのが当たり前に。
さらに、社会全体の高齢化が加速する中で、
「誰がどうやってお墓を守っていくのか?」という現実的な問題が浮かび上がっています。
年を重ねた親が遠方のお墓を維持するのも大変。
子ども世代も、忙しい日々のなかでお墓参りに通うのは簡単なことではありません。
「気持ちはあっても、続けていけない」
そう感じる人が増えているのが、今の日本のお墓事情です。
このような供養の“継続のむずかしさ”が、
のちに「墓じまい」という新しい選択へとつながっていくことになります。
墓じまいの増加が止まらない理由|背景とデータで読み解く供養の変化
最近、「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えてきたと感じている方も多いのではないでしょうか。
もともとはそれほど一般的な言葉ではなかったものの、今では“選択肢のひとつ”として広く知られるようになり、実際に行う人も年々増えています。
墓じまいとは、お墓を撤去し、遺骨を他の場所に移すこと。
移転先としては、納骨堂や永代供養の施設、樹木葬や海洋散骨など、多様なスタイルがあります。
そうした背景には、家族の形やライフスタイルの変化があります。
「家族に迷惑をかけたくない」「子どもが遠方に住んでいる」「そもそも継ぐ人がいない」
そうした現実的な理由から、“お墓を整理する”という選択は、もはや特別なことではなくなってきました。
実際、厚生労働省の統計によれば、2023年度の改葬件数は全国で166,886件。
20年前(2003年)の約38,000件と比べると、4倍以上に増加しています。
※引用元(衛生行政報告例)
もちろん、すべてが墓じまいに該当するわけではありません。
引っ越しや合葬なども含まれますが、「お墓を移動させる」こと自体が、いまや多くの人にとって選択肢のひとつになっていることは間違いありません。
【地域別】お墓の違いはなぜ?寺院数・文化から見る地域差
お墓のあり方は、日本全国どこでも一律ではありません。「どんなお墓を建てるか」「どこに供養するか」は、その土地の歴史や文化、地価、人口構成などによって、大きく変わります。
ここでは、地域ごとの特徴がどのようにお墓や供養スタイルに影響を与えているのかを見ていきましょう。
寺院数が多い都道府県ランキング
お墓を語るうえで、まず注目したいのが「寺院の数」です。
とくに地方では、今でも菩提寺(先祖代々のお寺)とのつながりが強く、お寺の敷地内にお墓を建てる家庭も少なくありません。
文化庁『宗教年鑑 令和6年版』によると、仏教系の宗教団体(≒寺院)は全国におよそ76,000か所存在しています。中でも寺院数が多い上位の都道府県は以下の通りです。
.webp) (出典:文化庁『宗教年鑑 令和6年版』)
(出典:文化庁『宗教年鑑 令和6年版』)このように、仏教文化の影響が色濃く残る西日本の府県が上位を占めています。
なぜ関西圏に寺院・墓地が集中しているのか?
関西圏に寺院が多い理由の一つは、歴史的な仏教の中心地であったことにあります。
京都や奈良は古都として知られ、飛鳥時代から続く寺院が今でも多く残っています。
また、江戸時代には「檀家制度」によって、地域の住民が必ずどこかの寺院に属する仕組みが確立されました。
とくに関西ではこの制度が深く根付き、結果として「地域ごとに密に配置された寺院」が残りやすかったといえます。
こうした背景から、関西圏では今でもお寺と墓地の結びつきが強く、
「お墓=寺の中にあるもの」と考える人も少なくありません。
都市部は納骨堂・永代供養型が主流に
一方で、東京や大阪、横浜といった都市部では、近年「納骨堂」や「永代供養墓」が主流となりつつあります。
その背景には、ライフスタイルの変化があります。
都心に暮らす人ほど「墓守りが難しい」「後継ぎがいない」という悩みを抱えやすく、
“管理不要で預けられる供養”を求める傾向が強まっているのです。
また、納骨堂は屋内施設のため、アクセスも便利で天候に左右されにくいという利点も。
駅近で見学できる施設も多く、「いざという時に困らない」選択肢として、都市部の支持を集めています。
地価やスペースが供養スタイルを左右している
さらに供養スタイルの違いに影響を与えているのが「地価と土地の広さ」です。
都市部では土地そのものが高価かつ限られているため、広い区画を使う一般墓よりも、
コンパクトな納骨型や合葬墓の方が現実的とされています。
たとえば東京都内では、人気の都立霊園の倍率が数十倍にもなり、一般墓の取得は非常に困難。
結果として「納骨堂」「樹木葬」「合葬墓」など、スペース効率を意識した供養スタイルが増加しています。
逆に地方では、地価が安く、家族で墓地を継ぐ文化も残っているため、今でも伝統的な“家墓”を選ぶ人も少なくありません。
【墓地の倍率事情】人気霊園は数十倍の抽選も!?2025年の現状
人気の公営霊園や都立霊園では、申込みに対して当選倍率が数倍〜数十倍になることも珍しくありません。
「お墓を建てよう」と思っても、場所が確保できない時代が、すでに始まっているのです。
このパートでは、実際の倍率データを見ながら、現代の“墓地事情”について考えてみましょう。
東京都立霊園の倍率と特徴(多磨・青山など)
東京都が管理する都立霊園は、立地の良さ・管理の安心感・使用料の安さなどから、毎年多くの応募が集まる人気の霊園です。特に注目されているのが、多磨霊園(府中市)や青山霊園(港区)といった、歴史と規模を兼ね備えた霊園。
2024年度(令和6年度)の募集では、以下のような倍率が発表されています。
※参考文献:東京都 都立霊園の使用者募集結果(2024年度)
● 青山霊園(一般埋蔵施設):倍率13.0倍
● 多磨霊園(芝生墓所):倍率2.0倍
青山霊園は港区という都心立地の希少性もあり、わずかな募集区画に希望者が集中。
「当たればラッキー」と言われるほど、極めて高い競争率となっています。
一方、多磨霊園は都立霊園最大級の広さを誇り、比較的倍率は落ち着いているものの、毎年安定して人気を集める霊園です。
芝生墓所・一般墓所ともに、整備された環境と交通アクセスの良さが支持されており、応募者が絶えることはありません。
横浜・名古屋・大阪などの公営霊園の倍率動向
地方都市においても、公営霊園の倍率は年々高まりを見せています。
とくに都市部では「アクセスの良い公営霊園」は非常に限られているため、毎年の応募には激戦がともないます。
● 横浜市(2024年 メモリアルグリーン)
芝生型納骨施設一般墓所:8.5倍 ※参考文献(横浜市営墓地メモリアルグリーン)
● 名古屋市(2022年 八事霊園)
一番高い区画:約4倍 ※引用元(有限会社光徳石材)
● 大阪市設霊園(瓜破など)
抽選倍率は非公開ですが、毎年の募集枠が非常に少ないため、高倍率が予想される状態です。特に都市部近郊の区画は人気が集中します。
このように、都市部の公営霊園は「立地」「価格」「管理の信頼性」から高い支持を集めており、今後さらに競争率が上がることも予想されます。
倍率が高くなる背景にある“供養の集中化”
公営霊園の倍率が高くなる背景には、単なる「人気」だけでなく、社会全体の供養スタイルが都市部に集中しはじめているという構造的な変化があります。
都市部に集中する“供養ニーズ”
かつては、地元の菩提寺にお墓を建てるのが一般的でしたが、核家族化・都市への人口流入・ライフスタイルの変化により、「家族が集まりやすい都心や近郊にお墓を求めたい」と考える人が増えています。
通いやすさ、将来の継承のしやすさ、老後の備えとして「自宅近くの霊園を確保しておきたい」という思いが、特に中高年層を中心に高まっているのです。
公営霊園は「安心・安価・信頼」の三拍子
さらに、公営霊園は、
●永代使用料や管理費が民間に比べて安価
●地方自治体が運営しているため管理に対する安心感がある
●長期的に使えるという将来の不安を減らせる設計
といった利点があり、「選ぶならまずは公営霊園から」と考える人が多いことも、倍率を押し上げている要因のひとつです。
今後、墓地はますます“取りづらくなる”のか?
結論からいえば、墓地の確保は今後さらに難しくなる可能性が高くなるといえます。
その理由は、需要と供給のバランスが大きく崩れはじめているからです。
増え続けるニーズ
高齢化の進行により、供養先を考える人が年々増えています。
さらに最近では、一度お墓を片付けた人が“新たな供養先”を求めるケースも増加しています。
たとえば「実家のお墓を墓じまいしたけれど、自宅近くにあらためて納骨したい」といったケースです。
こうした再需要によって、ひとつの霊園に対して応募が集中しやすくなっているのです。
将来的に予想されること
公営霊園の新設は年々難しくなっています。
特に都市部では、霊園用地を新たに確保するのが極めて困難です。
返還区画の再利用や既存エリアの再整備で対応しているものの、供給数には限界があるのが現状です。
人口密集地では開発可能なスペースが限られており、霊園よりも住宅や商業施設が優先されがちなのが現実です。
そのため、現在の公営霊園は
・返還された区画を再利用
・園内の一部を整備して再募集
といった形で対応していますが、供給できる数にはどうしても限界があります。
今後も大きく区画を増やす見込みは薄く、「供給は横ばい or 減少」「需要は上昇」というミスマッチが続くことが予想されます。
そのため、早めの情報収集や、霊園以外の選択肢(納骨堂・樹木葬・合葬墓など)を含めて柔軟に検討することが大切です。
墓じまいの流れや手続きについては、「実際にやるとなったらどうする?」という声も多く聞かれます。
具体的な進め方や必要書類、費用相場などについては、こちらの記事をご覧ください。
[墓じまいの費用等について]
広がる“お墓を持たない”選択肢|新しい供養のかたち
今では、“お墓を持たない”供養のかたちを選ぶ人も確実に増えています。
そこには、「残された家族に負担をかけたくない」「自分の意思で供養の形を選びたい」という、今の時代ならではの想いがあります。
海洋散骨・樹木葬・手元供養・納骨堂の特徴
近年、従来のお墓に代わる供養スタイルとして、以下のような方法が注目を集めています。
▷ 海洋散骨
故人の遺骨を粉末状にし、海へ撒くという供養スタイル。
自然に還るという発想から、環境志向の強い方や“帰る場所は自然でいい”と考える人に支持されています。
【特徴】お墓を持たずに供養が完結。家族でクルーズ式のセレモニーを行うケースも。
【向いている人】お墓の管理を求めない人/自然葬に共感する人
▷ 樹木葬
墓石の代わりに樹木の下に遺骨を納めるスタイル。
個別型や合葬型があり、自然と共に眠るという“やさしい供養”として人気が高まっています。
【特徴】墓標の代わりに木や花が植えられる。永代供養とセットのケースが多い。
【向いている人】自然志向・管理を委ねたい人/霊園に通えない人
▷ 手元供養
遺骨の一部を手元に保管したり、アクセサリーに加工して身につけるスタイル。
「近くに感じていたい」という想いに応える供養法です。
【特徴】自宅で保管できる。骨壺・ジュエリーなど多彩な形がある。
【向いている人】故人との距離を感じたくない人/お墓を持たない暮らしを望む人
▷ 納骨堂
建物内に遺骨を安置するスタイル。都市部を中心に急増しています。
【特徴】駅近やビル型もあり、天候・距離に左右されずお参り可能。
【向いている人】通いやすさ重視/管理不要を望む人
「お墓を建てない供養」を選ぶ理由
多くの人が“お墓を持たない供養”を選ぶ理由はさまざまですが、大きく分けて以下のようなものがあります。
① 継承者がいない
少子化や未婚率の上昇により、「お墓を継ぐ人がいない」という家庭が増加。
結果として、「自分の代で完結する供養」が求められるようになっています。
② 負担をかけたくない
「子どもに管理の負担をかけたくない」「金銭的にも精神的にも、軽くしてあげたい」という親心から、あらかじめ自分で“墓を持たない”供養を選ぶケースも。
③ 気持ちの問題
「お墓がないといけない」という考え方にとらわれない人が増えたことも大きな背景です。
故人のことを想う気持ちさえあれば、形式は自由でいい──そう考える人が増えた今、供養のあり方も柔軟になっています。
まとめ|変わりゆく日本のお墓と、これからの供養のかたち
日本におけるお墓のかたちは、確実に変わりはじめています。
昔ながらの“家墓”だけでなく、納骨堂・樹木葬・海洋散骨といった多様な選択肢が登場し、
「どこに眠るか」ではなく「どう送りたいか」が重視される時代になりました。
家族の負担を減らしながら、想いを大切にしたい──
そんな現代のニーズに応える供養を、今こそ見つめ直す時期にきているのかもしれません。
自分らしい供養のかたちは、一人ひとり異なって当然です。
海への散骨にご興味を持たれた方は、流れや費用について、ご不明点などお気軽にご相談ください。
初めてでも安心して相談できる窓口をご用意しています。
お問い合わせはコチラ▶【銀河ステージお問い合わせ】